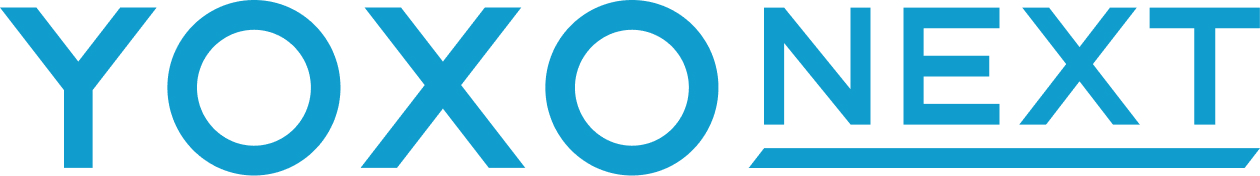横浜市経済局ビジネスイノベーション部イノベーション推進課
担当課長 倉持知子、担当係長 濱田洋平、担当 平本航
次世代起業人材育成事業受託事業者
株式会社plan-A 代表取締役社長 相澤毅、プログラム担当 田中優子、地域連携マネージャー 澤田珠里
横浜市のスタートアップ成長支援拠点「YOXO BOX(よくぞボックス)」が、2025年度にその役割をアップデートします。
新たな視点で課題解決を目指す起業家や中学生・高校生を含む若年層を「次世代起業人材」ととらえ、横浜に暮らす未来世代の人生の選択肢に「起業」をインプットし、横浜をもっとワクワクできる街にしていく──。そんなプロジェクトをスタートしました。
横浜市経済局ビジネスイノベーション部イノベーション推進課・倉持知子、濱田洋平、平本航と、本事業の運営者・株式会社plan-Aの相澤毅、田中優子と澤田珠里の対談で、YOXO NEXT(よくぞ・ネクスト)について深掘りします。
YOXO BOXのこれまでとこれから

平本航(横浜市経済局): 「YOXO BOX」は旧市庁舎の向かい、横浜市中区尾上町に2019年10月(令和元年度)に開設しました。以来約6年間、スタートアップの成長支援拠点として運営し、「YOXOアクセラレータープログラム」や「YOXOイノベーションスクール」などの各種プログラムを走らせて、起業家のフェーズにあわせた成長支援を実施してきました。同時に起業家同士の仲間づくりや、支援機関・VC(ベンチャー・キャピタル)・大企業とのネットワーク構築をサポートも行っています。こうした取組の一つの成果として、横浜市の中期計画で掲げた「支援したスタートアップが受ける投資額」や「スタートアップの創出件数」の数値目標を毎年度達成することができました。しかし、「ユニコーン級のスタートアップを生み出す」という視点では課題が残りました。これまで幅広い分野の起業家を支援してきましたが、横浜の強みである大企業や研究開発施設、研究人材が集積していることを活かし、テック系スタートアップに特化した支援が必要と考えました。そこで2024年11月、みなとみらいにTECH HUB YOKOHAMAを新設しました。
もう一つの課題は、全国的な課題となっている起業人材の東京流出です。そのために、「起業するならやっぱり横浜だ」と思ってもらえる事業にしたいと考えました。起業に関心のある中学生・高校生が横浜の大人と関わりながらアントレプレナーシップを高める機会を創出するとともに、起業を志す皆さんに横浜で起業する魅力を感じていただけるよう、まちぐるみで起業を応援する「YOXO NEXT」プロジェクトを立ち上げることにしました。

相澤毅(plan-A): plan-Aは、JVの企業様と一緒にYOXO BOXの設置から関わっています。スタートして間もない頃は、横浜では「スタートアップ」という言葉が十分に浸透しておらず、地域のイベントで説明しても「カタカナで何のこと?」とネガティブな反応もありました。その一方で、横浜市では都心臨海部において、「文化芸術創造都市・横浜(クリエイティブシティ・ヨコハマ)」を掲げ、関内地区は特にアーティストやクリエイターの育成や集積を行い、十分な魅力や強みがある状況でした。そこに「スタートアップ」という新たな文脈を文化として根付かせるために、我々がYOXO BOXで行うプログラムを単発では終わらせずに、イベントやプログラムをスタートアップの方々と地域団体と共催で行うことで、まちの人たちに「スタートアップって何やってるの?」と聞かれなくなるまで認知を広げていくことを徹底しました。特に4年目以降は、「YOXO FESTIVAL」と「桜通りOPEN!」をからめることで、桜通りを会場に、まちのアーティストやクリエーターと一緒に、スタートアップも「創造者」として街に溶け込んでいく姿が見られるようになりました。
行政事業はどこかで期限がくるものなので、その事業が自然と地域に馴染んでいくようにならないと、まちの資産になりません。文化醸成の話なので、スタートアップをいかに街の文化に馴染ませていくかという地道な作業をずっとやってきた6年間でした。結果的にスタートアップ成長支援につながるということを仕掛けており、それが新事業の「YOXO NEXT」にめちゃくちゃ効いていると感じています。
── 文化を根付かせるという視点は重要ですね。スタートアップが街に自然と存在することが文化になれば、行政事業の期限が来ても資産として残ります。相澤さんが言うように、スタートアップという言葉を市民の共通言語にしたことが大きな功績だと思います。そんな「YOXO BOX」で、新しく「YOXO NEXT」がスタートする背景をもう少し聞かせてください。
YOXO NEXTへのリニューアルと狙い

倉持知子(横浜市経済局): YOXO BOXでこれまで支援してきた方々を見ると、地域や社会を変えたいという強い気持ちを持った人が多く、子育てや環境などに関する社会課題の解決を目指すスタートアップを中心に活躍されてきました。
私は今年からこの事業を担当しているのですが、外から見ていた時はYOXO BOXに少し敷居の高さを感じていました。スタートアップ成長支援という目的に特化していたので、利用者が限定的だった印象があります。今回、支援の軸と対象を見直し、より地域とつながる、より裾野を広げる方向へ舵を切りました。「次世代」というキーフレーズを掲げて中高生や若い世代の起業家精神を高める機会を提供したい。これは横浜だけでなく日本社会全体でも重要な課題だと思います。若者が横浜で学び、将来横浜で事業を起こすきっかけになれば、人口の定着や地域経済にとって大きな意味があります。それを公的な拠点で、中高生を対象に行う「YOXO NEXT起業ラボ」のプログラムは、全国的にも先駆的な取組になると思っています。
横浜は東京に近接している分、大学生くらいの年頃で、実家が横浜にあっても都心に通学する傾向が強いと思います。その結果、就職先も横浜である必要がなくなり、東京に近い利便性が逆に横浜の弱点にもなっていました。今回の取組がどこまでその課題にアプローチできるかは未知数ですが、中高生時代から地域で仕事をする人に関わる経験は、心の一番大事なところに響いてくるのではないかと思います。その一つのきっかけになるような事業を横浜の経済分野でやることが、横浜のユニークさ、魅力につながると思います。
── 市の担当者として、起業人材育成の将来イメージはどのように思っていますか?

濱田洋平(横浜市): 「YOXO NEXT 起業ラボ」を経験した方々には、いずれ横浜で起業してもらいたいと思いつつも、一足飛びにそこにいくわけではなく、将来の選択肢の一つに「起業」を入れてもらえればよいと考えています。担当者としては、息の長い事業としていきたいので、若い皆さんや保護者の皆様、地域の皆様から大切な事業だと思っていただけるよう、いただいた声をしっかり反映していきたいですね。そして、先輩スタートアップや地域の事業者など、起業を応援する大人たちにふれる機会をどんどん広げていきたいです。
相澤: 私は就職氷河期世代で、よい高校、大学に入り、いい企業に就職し、終身雇用とまではいかなくても、安定せよ、という流れが残っていました。だけど現実問題として、すでにその仕組みが壊れていて、今の中高生の親御さんはその事実を実感値ではわかっているはずです。
一方で、教育課程においては探究学習が進められていますが、社会経験上ビジネスや起業にふれていない教員の方々が探究学習のカリキュラムを組む際に、それを指導してくれる存在がいないという課題に直面しています。
YOXO NEXTは横浜市経済局の事業ですが、「あたり前がない時代」を生きていくなかで、「スタートアップにふれる経験」というのは、実は若年層だけでなく、保護者支援や教育行政など、さまざまな分野の方々に選択肢を与えることにつながり、行政事業としても他分野に波及していく可能性があると考えています。
中高生向け「YOXO NEXT起業ラボ」の連続性

田中(plan-A): 8月23日(土)と24日に、中高生向けの「起業ラボ」として各日4時間のワークショップを開催し、中学1年生から高校3年生まで、フェーズも価値観も異なる人たちが起業というテーマで集まりました。
1日目は「自分が起業するなら」という視点で、起業のタネを見つけ、チームで課題を探求し、解決策をアイデアとしてまとめ、最後に発表します。起業の出発点は「誰かの困りごとに気づくこと」ととらえ、解決策を考えることで、それが解決策をカタチにした「商品」アイデアのタネになるかもしれません。
2日目は先輩起業家をゲストに迎え、起業アイデアが生まれた経緯や苦労を聞き、その先輩が叶えたい夢を実現するアイデアをチームで考えました。両日とも最後に発表と振り返りのワークを通して「学んだことを自分の将来にどう活かすか」を考えてもらう時間も用意した。
このプログラムは「いますぐ起業するため」ではなく、「将来自分のやりたいことを叶える力をつけるため」のヒントとして起業を知ってほしいという想いで作りました。起業家は身近にいないことが多いので、実際に起業した人に会い、「こんな働き方もあるんだ」と知る機会を提供したいと思っています。
おかげさまで、ご好評をいただき、プログラムは大盛況に終わりました。さらに、先を見据えた仕掛けとして、参加者がその後も継続的に情報を受け取れるよう、公式LINEも開設しています。イベントレポートを配信したり、他のプログラムを案内したりして、参加者や保護者、先生、地域の方に「面白そう」と感じていただけるような情報を発信していきます。最初の体験があると次にこの場に来るハードルが下がり、中高生のお子さんを持つ親御さんにも、「あの場所なら安心」と思ってもらえたら嬉しいです。

濱田: YOXO BOXでは「挑戦者を称える」という精神をこれまでも掲げてきました。YOXO NEXTによって中高生向けのプログラムに限定されず、大人の起業家支援も継続的に実施していきます。世代を問わず挑戦する人が集まる場であり続けたいと思っています。
YOXO NEXTチームの皆さんが、誠心誠意でいいものにしようと、日々動いてくださっている。私たちも安心してワクワクしています。
── 中高生にとってYOXO BOXというリアルな場で学ぶ体験はとても貴重です。1日限りで終わらせず、卒業生的な帰属意識や継続の仕掛けがあるのはよいですね。
横浜愛で起業家とまちがつながる「YOXO NEXT 検証ラボ」
── YOXO NEXTでは「横浜がまちぐるみで起業を応援するまちに もっとワクワクするまちに」というビジョンを掲げており、YOXO BOXという施設内にとどまらない、一歩外へと踏み出した次世代起業人材育成という印象です。

濱田: 「YOXO NEXT起業ラボ」のターゲットは中高生ですが、次のステップとして提供するのが、起業家の事業アイデアのニーズ検証機会となる「YOXO NEXT 検証ラボ」です。様々な世代の起業人材が地域の多様な立場の方々とともに事業アイデアを磨いていくプログラムで今回2種類の検証ラボを実施します。1つ目は、例年多くの方が来場される「関内フード&ハイカラフェスタ」にて、来場される一般の方に向けて商品・サービスの展示等を行う機会を提供する「検証ラボ@展示会」です。2つ目は、事業者向け製品・サービスの検証の機会として、起業家の事業アイデアに関連する事業者の方と壁打ちなどができる機会となる「検証ラボ@伴走支援」です。起業家の事業アイデアが想定している顧客にもニーズがあるかをリアルに把握していただける機会となることを期待するとともに、地域の方たちに起業家と関わっていただく機会を創出したいという考えのもとで実施するものです。
検証ラボのほかにも、起業を通じて地域や生活に関する課題を解決したいと考えている方が起業に向けた実践的な学びを得ていただく講座の開設に向けた準備も進めています。起業家の新しい視点やアイデアで社会を変えたい、地域をよくしたいという思いと、地域の方たちの起業家を応援する思いを交差させながら、「横浜クロスオーバー=YOXO」の“挑戦を称える”カルチャーを引き継いでいきたいと思います。
相澤: YOXO NEXTの事業をつくるにあたり、「なぜ横浜?」を真剣に突き詰めないと、持続可能なものにならないと、何度も議論を重ねてきました。横浜に対する想いの強さがあるから横浜を知ろうとする循環が起こります。「横浜愛」がなければ、東京がこの近い距離にあるので、「スタートアップするなら東京でいいじゃん」になってしまいます。あえて横浜を選んで起業し、横浜で成長したい人にとって、我々地域側がその価値を打ち出せなければ、横浜にいてもらえないだろうと思います。
私は、東京流出そのものは悪いことではなく、人生のどこかで東京を経験すべきだと思いますが、「横浜で錦を飾りたい」「やっぱ横浜なんだ」と思ってもらうには、そのための原体験が必要です。横浜独特のスピード感や、まちとしての居心地のよさ、おもしろさは、個別の原体験に基づいたものすごく定性的な話です。「横浜ならば何かできるかもしれない」という思いとアクションをどう引き出していくのか、たとえばみなとみらいのR&Dや、国際的に注目される瀬谷エリアなど、実証実験ができるフィールドが豊富にあるのが横浜です。これを“撒き餌”にして東京にはない横浜ならではのどう価値を構築できるのかを真剣に検討していかなければなりません。

倉持: 私は横浜育ちで、純粋に横浜が好きです。行政の仕事を通して感じるのは、部局を超えてミッションに取り組むときなど、市職員がそれぞれに横浜をより良くしたいという思いを持ち寄って積み重ねながら、このまちをつくってきたということです。YOXO BOXの取組もまちづくりの側面があると考えており、この取組が次の世代につながっていると思います。
ワクワクを横に繋いでいく地域連携マネージャー(ちいマネ)
相澤: 今後、YOXO BOXで中高生も含めた新たなコミュニティを作っていくにあたって、「特定のスタートアップが集まる場」から脱却し、地域の人や様々な事業者が出入りしやすい環境を整えていきます。そこで、YOXO BOXの中にいる人たちをよく知り、その人たちに何ができるか把握したうえで外の人とつなぐ「地域連携マネージャー(通称:ちいマネ)」を置くことにしました。彼らは来訪者をウェルカムに受け入れ、スタートアップ側にも「こんな人がいますよ」と自然な形で紹介する役割を担います。一方で、YOXO BOXに集う起業家のこともあまねく理解する必要があり、起業家や地域が何を求めているのかを収集して、適切な拠点や人につなぐ役割も期待しています。YOXO BOXは公民館のような場所ではなく、オープンだけれど秩序あるコミュニティ。それを支える存在が「ちいマネ」です。

澤田珠里(plan-A): 実は最初に「ちいマネ」という言葉をつくって、そこから「地域連携マネージャー」という役割が生まれていきました。既存のコミュニティマネージャーとは少し違い、コミュニティと地域を結ぶ窓口となる存在です。民間のインキュベーション施設や他の公的拠点とも連携し、YOXO NEXTだけで閉じずに横浜全体のイノベーション・エコシステムとつないでいくパイプ役になるのが私の役割です。例えば、オープンイノベーションに興味のある方なら、神奈川県の「SHINみなとみらい」につなぐこともあるでしょうし、テック系ならば横浜市のTECH HUB YOKOHAMAといった、他拠点に興味を持った参加者やスタートアップを適切な場所へ橋渡しすることも役割の一つです。YOXO BOXはもちろんのこと、横浜市の他事業や、今年度より連携を始めた神奈川県のベンチャー支援の各種事業へのおつなぎもできます。
今、いろいろな方に事業の説明をしている最中ですが、この事業のことを誰かに話すたびに「いいことやっているね!」と、応援してくれて、一緒にワクワクしてくれているのを感じます。
田中: 参加者の方を集めてプログラムを行うだけではなく、YOXO NEXTが目指す「横浜がまちぐるみで起業を応援するまちに もっとワクワクするまちに」を体感してらうためにも、ちいマネもプログラムに入ってもらっています。その後参加者がYOXO BOXに来た時に「あの時いた人がここにいる」という連続性を埋めるのも、事業に関わる人やコミュニティが分断していないからこそできることです。
ワンチームでYOXO NEXTを作るぞという気持ちを共有してやれていることが、とてもうれしいです。私にも小学生の子どもがいるのですが、自分の子が中学生になったら参加してほしいと思える事業を作れていることに喜びを感じています。

平本: 大変なこともたくさんありますが(笑)、それでもこのチームでの仕事にはワクワク感があります。こういう大人の姿を子どもたちに見てもらえると、本当はいいよなあと思っています。
相澤: 関わる人たちが共に汗をかき、ワクワクを共有することが成功の鍵だと思います。
自分たちはそれぞれ子育て当事者として、スタートアップに近しいところにふれる体験が小さいころにどれだけあるかで、その子の人生が変わっていくのではないかと考えています。起業家マインド醸成の源泉を、我々はわが子たちに見ているのです。
ひるがえって横浜市として見た時に、いろんな可能性を示せるポテンシャルがある街だと思います。みんながちょっとずつ越境していけば、それぞれが足りないものが面になり、行政事業の限界を飛び越えてつながり始め、本来エリアや横浜市におこすべき現象を実現していけるのではないかと思います。みんながつながり始めると、「あれ、越境できている、クロスオーバーできているじゃん」と気づき、ポジティブな思考になっていくはずです。ワクワクする好循環。YOXO NEXTはそれを実現できるプラットフォームなのです。

── 行政担当者も運営者も、自らワクワクしながらこの事業に取り組んでいること。行政・民間・地域が一体となり、泥臭くも熱量を持って次世代を育てようとする姿勢そのものが「YOXO NEXT」の魅力であり、未来の起業家やまちづくりにつながっていく希望が見えてきます。

Information
●YOXO NEXT起業ラボ|記者発表記事
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/press/keizai/20z1z125/yoxonext_kigyorab.html
●2025年8月に実施した初めての起業ラボの募集記事(plan-A 特設サイト)
https://plan-a-02.co.jp/news/yoxonext-2025/